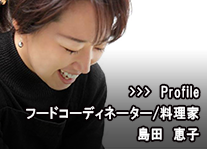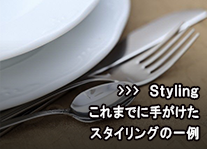東北ツーリング2018 大潟村編
2018年09月01日
今回の旅の1番の目的は、教科書でしか見たことがない八郎潟を見たくて、
大潟村の農家さんを訪ねました。
八郎潟は、琵琶湖についで日本で2番目に大きな湖でしたが、
国の政策で干拓よって陸地化され、大潟村ができたのが50年前のことです。
教科書の中でしか知らなかったので、ものすごく昔だと思ってましたが、
まだ50年前のできごとなんだ!
大潟村は、米の優良農地のモデル都市になるべく設計された土地で、
全国から入植者を募り、2,463人の中から589人が選ばれたそうです。
今も、入植者の方が現役で働いていらしたりします。
湖の底だった土地なので、整地したとはいえ、泥地。
大きな農機具が重くて、粘土質の地面にずぶずぶ沈んだり、
ハマったりする光景がよく見られたそうです。
大潟村干拓博物館での展示を拝見し、当時の方々の熱い想いと苦労が偲ばれて、
人の英知ってすごいなって改めて思いました。

今では、見渡す限りフサフサの田んぼです。

今回伺わせていただいた黒瀬農舎さんは、農薬や化学肥料に依存しない米作りをなさっています。
作っていらっしゃる品種は「あきたこまち」。そのほかにも餅米も作っていらっしゃいます。
田んぼをご案内いただき稲穂に近づくと、バッタやイナゴが慌てて逃げていったり、
カエルの鳴き声が聞こえます。稲穂が風にそよぐ音が心地よいです。
稲が小さいときに、鴨のヒナを借りてきて放し、
虫を食べてもらったり、田んぼの中で遊ぶことで水が濁って日光を遮り、
雑草が育たないようにするそうです。
倉庫を案内していただくと、私の好きなキャタピラーのついた重機が複数ありました。
とにかく大きな機械がいっぱい。
土地が広大なので機械を使うことが前提の農業です。
北海道や長野の農家さんを思い出しました。
設備投資が必要なので個人の新規参入は難しい業種なんだと気づきました。
米は、選別したり、乾燥させたり、精米したりするから、
収穫して、そのまま出荷できないんだ。。。
黒瀬さんのところは2回も色彩選別にかけて、
不純物や色が変わった米などをはじき、
1.85mmメッシュにかけて大粒のものだけを選別していらっしゃいました。
米は温度と湿度を一定にするため、出荷する分だけ精米なさって冷蔵倉庫で保管なさってます。
ひんやりしてました。
通常はお米が出荷のメインですが、最近の個食ニーズも考え、
有機JASのレトルトごはんも作られたそうです。
現在、日本の人口の35%は一人暮らしです。2040年には40%になると言われています。
高齢者の一人暮らしが増えつつあることを考えても、この加工品は需要があると思います。
島田が個人的に好きだったのは、黒瀬さんのところの玄米甘酒です。
秋田のオリジナル麹の「あめこうじ」を使用し、甘みがあるけれどスッキリした後味の甘酒です。
普通に飲むのもいいけど、アイスにかけてデザートソースにしたり、
白玉とかお餅とあずきを入れてぜんざい風にしても、おいしいです。
黒瀬さん。本当にお世話になりました。
問い合わせ先
黒瀬農舎
秋田県南秋田郡大潟村西1-4-7
朝8時~夜8時
大潟村干拓博物館
秋田県南秋田郡大潟村字西5-2
9:00~16:30(※入館は16時まで)
4月~9月:毎月第2・第4火曜日
10月~3月:毎週火曜日
年末年始(12月31日~1月3日)
(火曜日が祝日の場合は翌日が休館)