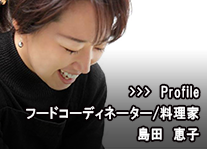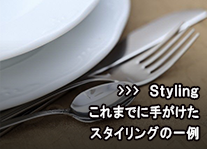枕崎の名人のかつおぶし。Vol.2
2018年11月09日
前回のおさらい。
鰹節をつくる工程で、生でも食べられる近海一本釣りのカツオを
包丁でおろして、茹でるところまで。
まだまだ工程長いけど、書ききれるかしら。
包丁でおろしたカツオの中骨から
スプーンで中落ちをこそげます。
このまま醤油つけて食べたいぐらい、おいしそう。
この中落ちを石うすに入れて、ペースト状になるまで練ります。
そういえば、カツオとかマグロもですが、
島田は刺身を食べたときに、鮮度がいいのに後味が酸っぱいって感じるときがありました。
魚は苦しんで死ぬと乳酸が出るので、まき網などで苦しんだ魚体は酸味が出るそうです。
鰹節にしたときにも、影響が出るので宮下さんのところでは、
一本釣りの魚体しか使わないそうです。
茹で上がってきたカツオの身から骨を抜き、
割れた身や傷に、先ほどの中落ちペーストを塗って整形します。
これをしないと傷から空気に触れるので、身の内側が酸化するのが早いそうです。
整形したカツオは、表面を固めるためと殺菌のために軽く蒸してから燻します。
鰹節を燻すことを「焙乾」というのですが、地域によって方法が異なります。
穴の中で薪を燃してせいろのようなもので焙乾する方法や
燻煙をファンで当てる方法がありますが、
枕崎では、天井の高い部屋を階層式にして下から炙りながら乾燥させます。
そうそう、薪ですが、枕崎には鰹節専門の薪屋さんがいるそうです。
枕崎の中で薪がこのような状態で積まれているところをたくさん見かけました。
広葉樹のクヌギ、サクラ、シイノキが中心で、近隣の山から集めてくるそうです。
山に囲まれた立地だから、ここで鰹節が作られてきたんだなって思いました。
焙乾し終えた鰹節は真っ黒です。
鮮度が悪いカツオだと黒くならないそうです。不思議。
焙乾後、日に当てて干してから表面の黒くてざらざらした部分を削ります。
削る前の鰹節は真っ黒です。これが荒節。
表面を削った鰹節は、裸節と呼ぶそうです。
これにカビつけしていきます。
そういえば、鰹節って最初カビつけしてなかったそうです。
関西から江戸に船で鰹節を送った際にカビてしまったのがはじまりだそうです。
下の写真はカビつけする前の裸節の鰹節。
今は、安定して使えるカビが無毒化された培養菌があるそうですが、
昔は、自然カビを使用していたので作ったかつおぶしの1/3に
悪いカビがついて捨てたこともあったと伺いました。
湿度の高いカビ付け用の部屋で何段階かに分けてカビ付けします。
カビ付けしたあとに天日で干します。
魚の切り身の状態から見てるので、あ。アノ尖ったところは魚の首のところ!
などと思いながら、眺めてました。
宮下さんのところで順調に製造すると
1本の枯節を作るのに4~6か月ほどかかるそうです。
さらに、タイコウさんのところで選別し、熟成させてから出荷するそうです。
なんて手間がかかる食材なんでしょう!
職人さんの技術のおかげで、おいしい鰹節が出来上がるのだと分かりました。
カツオ箱で削った宮下さんの鰹節は、ほんのちょっとでダシが出ます。
今まで、市販の削り節で取った出汁で感じてたカツオの酸味がありません。
なるほど、おいしいかつおぶしってこういうことか。
一般的に家庭で茶葉からお茶を入れたり、
かつおぶしからダシを引いたりすることが減ってきていますが、
気持ちに余裕がなくなってきているのかな?と思います。
要するには、鍋に湯を沸騰させてかつおぶし入れるだけです。
そんなに時間がかかる作業じゃありません。
確実においしいし、料理が楽しくなると思います。
ちなみに島田は、タイコウさんの本枯節の削り節「花くらべ」と
ダイスに切ったアボカドを醤油で和えて、
白いごはんに乗せて食べるのにハマってます。
お試しあれ。
かつおぶしが欲しくなった人はコチラから
かつおぶしのタイコウ